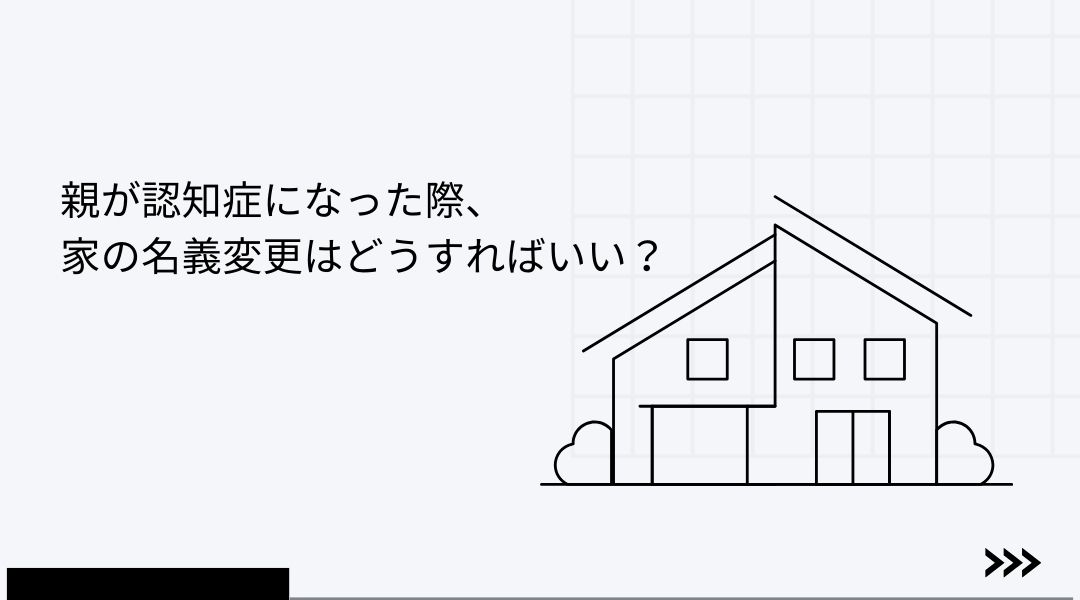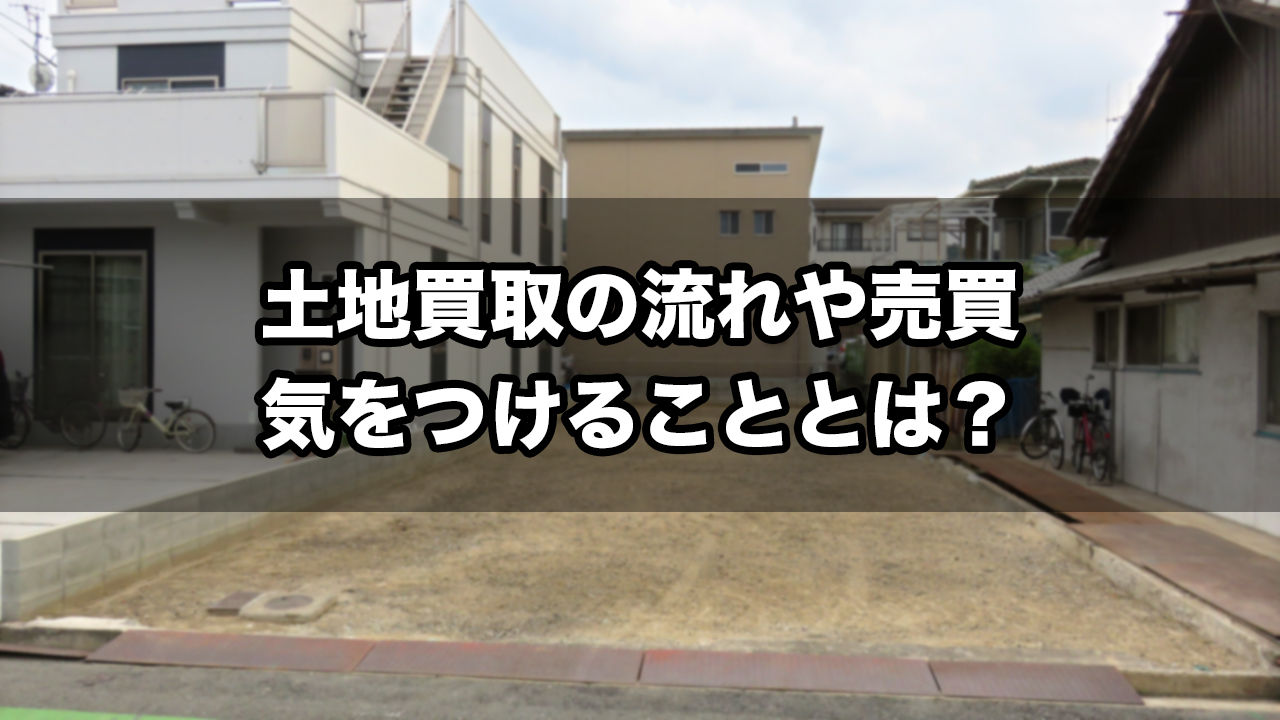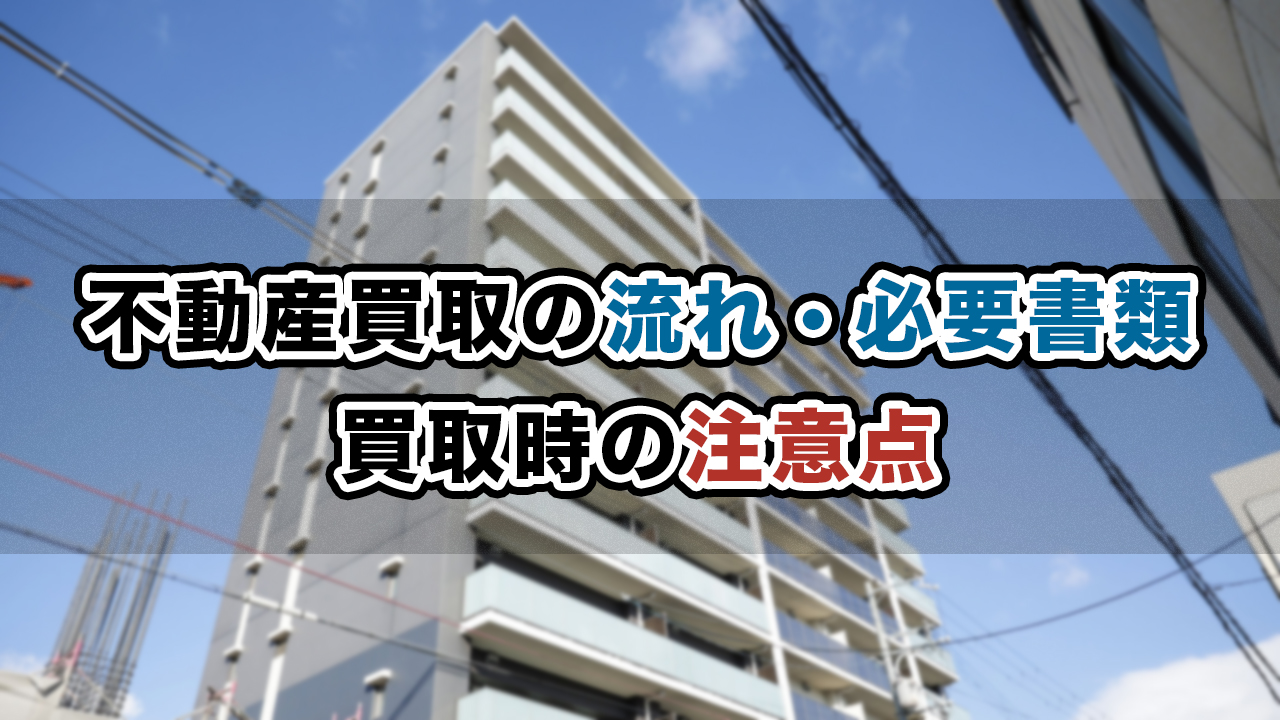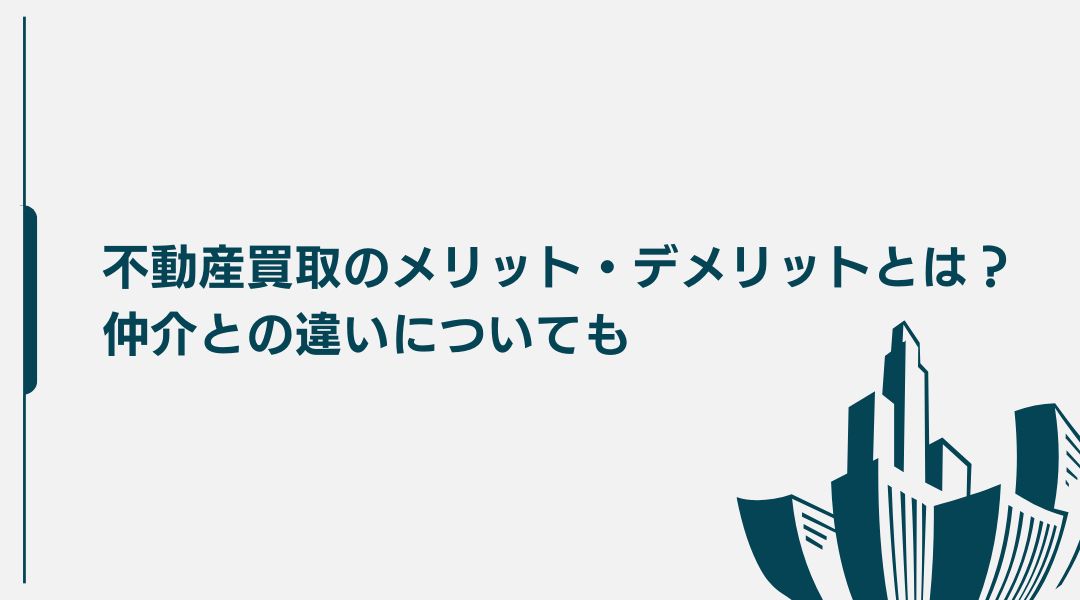親が認知症になったとき、家の名義変更はどうすればいいのでしょうか?この問題に直面する方は少なくありません。
認知症が進行すると、本人が契約や手続きの判断を適切に行えなくなるため、家の名義変更がスムーズに進まないことがあります。さらに、親の財産管理や相続の問題も絡み、手続きが複雑化するケースもあります。
では、どのような方法で名義変更を進めるのが適切なのでしょうか?
この記事では、親が認知症になってしまった際の家の名義変更について詳しく解説していきます。認知症になる前に対策する方法もご紹介していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
親が認知症になった際、家の名義変更は可能?
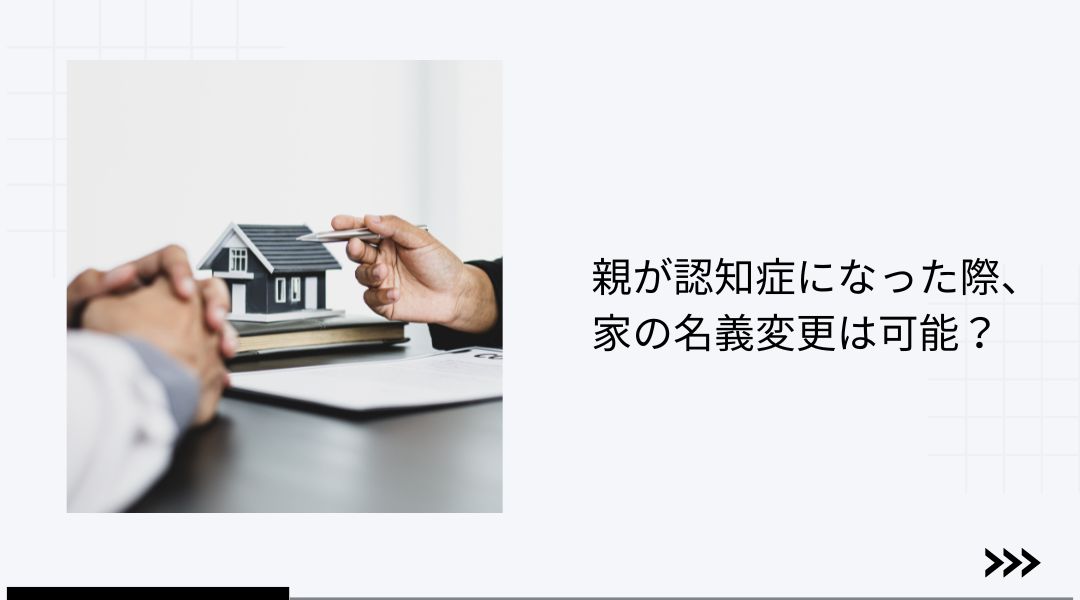
結論から言うと、認知症の進行により意思能力が失われた場合、家の名義変更に必要な契約行為(贈与や売買など)は無効となり、名義変更は事実上難しくなります。
親が認知症になった場合、家の名義変更が可能かどうかは、親の「意志能力」の有無に大きく依存します。意志能力とは、法律行為の内容とその結果を理解し、自らで判断できる能力のことを指します。
民法第3条の2で「法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする」と規定されています。
一方、認知症と診断されても、症状が軽度で意思能力が保たれている場合には、名義変更が可能なケースもあります。しかし、意志能力の有無は状況によって判断されるため、専門家から助言を受けることをおすすめします。
親が意思能力を失った後から家の名義変更を行う場合、次章で詳しく説明する制度の利用が必要となりますが、この制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要であり、手続きには時間と費用がかかります。
以上のことから、親が認知症を発症した場合、家の名義変更は状況によっては難しくなるため、親の意思能力が十分に保たれているうちに、家の名義変更や財産管理に関する対策を検討することが大切です。
親名義の家を名義変更する方法とは?

親が認知症の場合、その家の名義を子供に変更することは、法律的な手続きや親の判断能力の状態によって異なります。以下では、主な3つの方法を挙げ、それぞれ解説していきます。
1. 贈与による名義変更
親の家を子供に無償で譲渡する「贈与」は、一般的な名義変更の方法の一つです。しかし、贈与契約は法律行為であるため、親に「意思能力」が求められます。この意思能力とは、法律行為の内容と結果を理解し、自ら判断できる能力を指します。認知症の進行度によっては、贈与契約が無効となる場合もあるでしょう。
贈与を行う際に注意しておくべき点が贈与税です。年間110万円を超える贈与を受ける場合には税金が発生します。贈与税は税率が高いため、軽率な考えで贈与を行うと高額な贈与税を納めなければいけなくなる可能性がありますので、贈与を検討している方は専門家に相談することをおすすめします。
2. 売買による名義変更
親子間で不動産の売却を行うことで名義変更を行う方法もあります。この場合、親が子供に不動産を適切な価格で売却し、その対価を受け取る形となります。しかし、この売買契約も法律行為であるため、親の意思能力が問われます。贈与と同様に、認知症の親が法律行為の内容と結果を十分に理解できない場合、契約が無効となる可能性があります。
また、市場価格よりも低い価格で売買を行うと、差額分が「みなし贈与」とみなされ、税務署から贈与税が課される可能性があります。
3. 成年後見制度
親が認知症により意思能力を喪失した場合、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう方法があります。成年後見人は、親の財産管理や法律行為の代理を行う権限を持ちます。
しかし、成年後見制度の主な目的は親の財産保護にあります。そのため、成年後見人が親の家を子供に贈与や売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となります。また、成年後見人が親の家を子供に贈与することは、親の財産を減少させる行為とみなされるため、許可が下りない可能性があります。
このように成年後見制度の手続きには時間と費用がかかるため、事前に十分検討するようにしましょう。
事前に対策する方法は?

続いては、認知症の影響で家の名義変更が困難になる前の対策についてご紹介します。以下では主な対策方法「家族信託」「生前贈与」「任意後見制度」の3つを挙げ、それぞれ詳細に解説していきます。
1. 家族信託
家族信託とは、親が自身の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用を任せる制度です。この方法により、親が認知症を発症して判断能力が低下した場合でも、受託者が財産を適切に管理・運用できます。
家族信託の大きなメリットは、親の意思が明確なうちに契約を結ぶことで、後の財産管理や名義変更がスムーズに行える点です。親の介護費用や生活費を家族信託の財産から支出したり、親が亡くなった後は、家族信託の契約内容に従って財産を承継したりすることができます。成年後見制度と比較して、財産管理の柔軟性が高く、家族の意向に沿った運用が可能です。
ただし、信託契約の内容や受託者の選定は、慎重に検討する必要がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
2. 生前贈与
生前贈与とは、親が元気なうちに自身の財産を子供や孫に贈与する方法です。認知症になる前に家や土地を贈与することで、親の意思能力が問われる心配がありません。
生前贈与を活用することで、相続時の税負担を軽減する効果も期待できます。しかし、贈与には贈与税が課されるため、非課税枠(年間110万円)を超える贈与には注意が必要です。
また、生前贈与を行う場合は、遺留分に注意する必要があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が相続財産のうち最低限受け取ることができる割合のことです。生前贈与によって遺留分が侵害された場合、後々トラブルになる可能性があります。
3. 任意後見制度
任意後見制度とは、親が意思能力を有している間に、今後意思能力が低下した場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)に財産管理や生活支援を委任する契約を結ぶ制度です。
この契約は公正証書で作成され、親の意思能力が低下した際に効力を発揮します。任意後見制度を利用することで、親の意思に基づいた財産管理が可能となり、家の名義変更や売却などの重要な手続きもスムーズに行えます。
任意後見制度の注意点としては、家庭裁判所の関与や任意後見監督人への報酬支払いが発生することです。また、本人の財産と生活を守るための制度であるため、積極的な資産運用や財産が減少するような行為は制限されます。
まとめ
今回は、親が認知症になった際の家の名義変更について解説してきました。
認知症の影響により意思能力が低下してしまった場合は、家の名義変更が困難になります。民法では意思能力がない場合、法律行為は無効とされており、認知症が進行すると贈与や売買による名義変更は難しくなります。ただし、症状が軽度で意思能力が保たれていれば名義変更が可能な場合もあります。
名義変更の主な方法として、贈与・売買・成年後見制度の3つが挙げられます。贈与と売買に関しては、意思能力がないと利用することができません。成年後見制度を利用すると、家庭裁判所の許可が必要で時間と費用がかかります。
認知症対策としては、家族信託・生前贈与・任意後見制度が有効です。家族信託は財産管理の柔軟性が高いです。生前贈与は節税になりますが贈与税には注意が必要です。任意後見制度を利用すれば、将来の財産管理を信頼できる人に託すことができます。
意思能力を失ってからの名義変更は困難なので、早めに専門家に相談し、最適な方法を選択することをおすすめします。
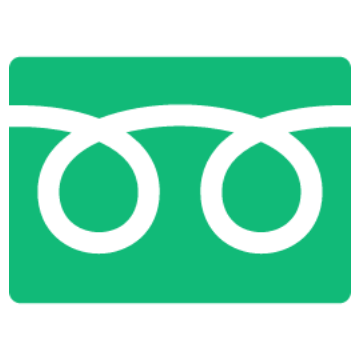 0120-210-400
0120-210-400