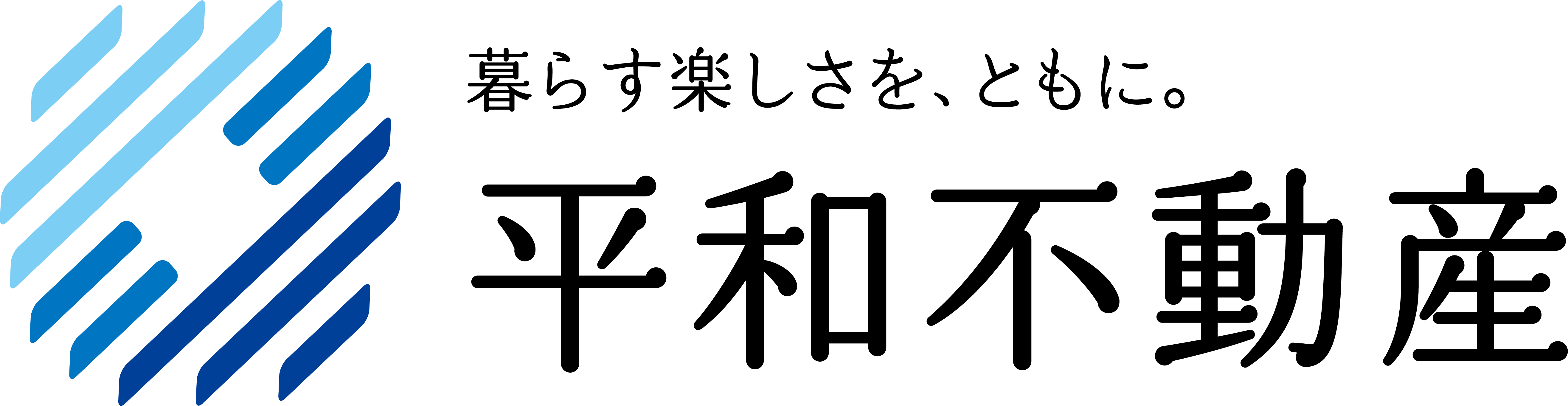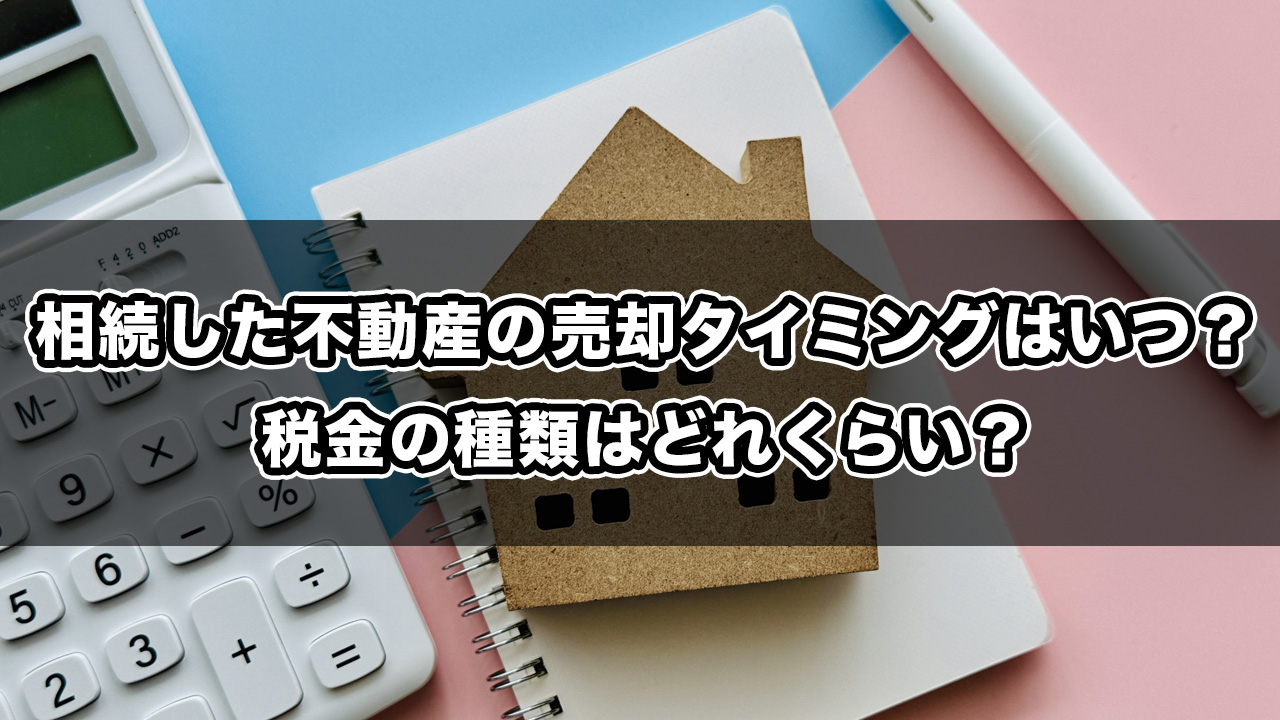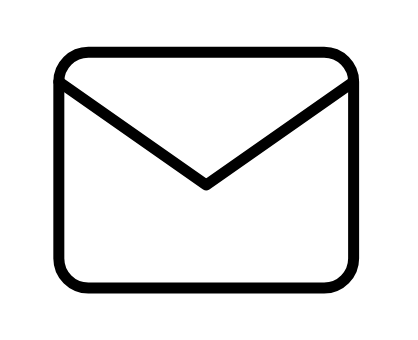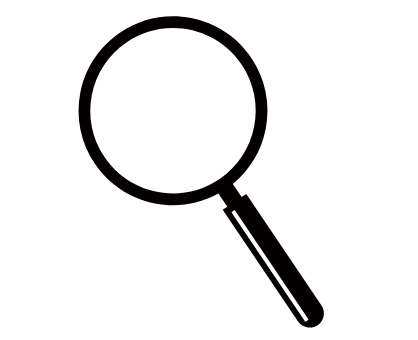親族から不動産を相続したとき、多くの方が悩むのが「この不動産をどうするべきか」という問題です。今後活用する予定がない場合、売却を検討する方も少なくありませんが、焦って手放すのは得策ではないかもしれません。
不動産の売却にはさまざまな税金が関わっており、タイミングによって支払う額が大きく変わることもあるためです。また、相続した直後と数年後とでは、手続きや課税内容も変化する場合があります。
そもそも、どんな種類の税金が発生するのか、売却時に注意すべきポイントとは何なのか。これらを知らずに進めると、損をしてしまう可能性があります。
そこでこの記事では、相続した不動産を売却するタイミングや、税金の種類について詳しく解説していきます。
相続した不動産の売却タイミングについて

不動産を相続したときに多くの方が悩むのが「今すぐ売却すべきか、それとも保有すべきか」という点です。売却するタイミングを見誤ると、税金面で損をする可能性があります。
以下では、すぐに売却するべきケースと、売却を急がない方がよいケースを解説していきます。
相続した不動産をすぐ売却するべきケース
1. 相続税を納税した
相続税は原則として現金一括での納付が求められます。不動産を相続した際にすでに納税を済ませた場合、その分の資金的な負担が大きくなっている可能性があります。
資金繰りや将来のリスク、税制特例を考慮した上で不動産を売却して現金化する判断を行うと良いでしょう。特に、維持費が高い不動産であれば、売却によって負担を減らすことができるでしょう。
2. 相続税の納税資金が無い
相続税の納税期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。この期間内に納税資金を用意するのが難しい場合、不動産を売却して納税資金を確保するのが現実的な手段です。また、不動産はすぐに売れるとは限らないため、早めの準備と売却活動が求められます。納税を延滞すれば罰金などのペナルティも発生するため、注意しておきましょう。
3. 相続した不動産の活用予定が無い
今後住む予定や貸す予定もなく、明確な活用計画が立っていない不動産は、所有しているだけで固定資産税や維持管理費といったコストがかかり続けます。また、空き家は劣化が早く、資産価値が下がる恐れもあるため、早期売却を検討する必要があるでしょう。
相続した不動産をすぐ売却しないケース
1. 税金を納める余裕がある
相続税の納付がすでに完了しており、なおかつ資金的な余裕がある場合は、不動産の売却を急ぐ必要はありません。資産価値の上昇を待ってから売却すれば、より高値での売却ができる可能性もあります。納税のために急いで売却すると、安値で手放す結果になってしまう恐れがあるため、余裕がある場合はすぐに売却する必要はないでしょう。
2. 相続した不動産を活用する予定がある
相続した不動産を賃貸物件として運用したり、将来的に自分が住む予定がある場合は、すぐに売却する必要はありません。不動産を収益物件として保有すれば、安定した家賃収入が得られることもあり、資産としてのメリットを活かすこともできます。立地が良く、需要が見込めるエリアの物件であれば、中長期的な活用を検討しましょう。
3. 遺産分割に問題が無い
相続人間で遺産分割に関する合意が取れており、不動産の共有者がいない、もしくは共有者全員の意見が一致している場合は、売却を急ぐ必要はありません。逆に、遺産分割の協議がまだ済んでいない状態での売却はトラブルのもとになります。
相続した不動産を売却した際の税金について

不動産を相続した際には相続税という税金がかかりますが、売却時にも別の税金が発生します。正確な知識を持っておくことで損を避けることができるでしょう。以下では、不動産を売却した際に発生する税金について解説します。
住民税
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して所得税だけでなく「住民税」も課されます。住民税は居住地の自治体に納める地方税であり、譲渡所得の金額に対して5%(長期譲渡の場合)が課税されます。
たとえば、不動産を売却して500万円の利益が出た場合、そのうち約25万円が住民税として課される計算です。特例があれば軽減措置を受けられる場合もありますが、原則として避けられない税金のひとつですので、事前に計算しておくことが大切です。
譲渡所得税
不動産を売却して得た利益には「譲渡所得税」がかかります。相続不動産の場合でも例外ではありません。譲渡所得は「売却価格 -(取得費+譲渡費用)」で算出され、この利益に対して税金が課されます。所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」として所得税30%、5年以上なら「長期譲渡所得」として所得税15%と低くなります。相続不動産の場合、被相続人の取得日を基準として所有期間が計算されるため、相続直後でも長期譲渡に該当するケースが多いです。
ここで注意すべきが「復興特別所得税」です。これは東日本大震災の復興財源として2037年まで導入される税であり、所得税額の2.1%が加算されます。つまり、長期譲渡所得の場合にかかる実質的な税率は「所得税(15%) + 復興特別所得税(0.315%) + 住民税(5%)」=計20.315%になります。
相続した不動産を売却した際のメリット・デメリット

相続した不動産を売却するかどうかは、多くの方が悩むポイントです。売却すると現金化や管理負担の軽減などのメリットがありますが、一方で税金や思わぬコストが発生するデメリットもあります。ここでは、メリット・デメリットについて具体的に解説します。
メリット
相続した不動産を売却する最大のメリットは、資産の現金化によって自由な資金が得られる点です。売却することで相続税の納税資金を確保できたり、自身の生活に応じた使い道が可能になります。特に、相続不動産が遠方にあったり、自分では使い道が無い場合、売却によって管理の手間や維持費の負担から解放されます。
また、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得として税率が低くなるケースも多く、税負担を抑えながら売却できる可能性もあります。さらに、一定の条件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」などの特例を利用することもでき、節税効果が期待できます。
一定の条件とは、
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 被相続人が居住していた
- 相続人が売却前に賃貸等していない
等があります。このように、売却は資産の有効活用や相続後の負担軽減という面でメリットが多いです。
デメリット
一方、相続不動産を売却する際にはいくつかのデメリットも存在します。
まずは、不動産の売却益に対する「住民税」「譲渡所得税」「復興特別所得税」の負担です。軽減措置が適用されない場合、譲渡所得に対して約20%超の課税が発生し、予想以上の納税額となることもあります。また、不動産の売却には登記費用、不動産仲介手数料、測量費などの諸経費がかかり、最終的に手元に残る金額が大きく減ってしまうケースもあります。
さらに、相続人が複数いる場合には、不動産を誰がどのように扱うかという点で意見が分かれ、売却手続きが遅れたりトラブルに発展する可能性もあります。単純に現金化だけを目的にせず、不動産の価値や相続人間の状況を総合的に考慮した判断が必要です。
相続した不動産を売却する流れ
1. 遺産分割協議
複数の相続人がいる場合、まずは「誰が不動産を相続するか」を決める必要があります。これを話し合いで取り決めるのが遺産分割協議です。協議が整ったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面化し、全員の署名・押印を行います。この書類が後の登記手続きや売却活動に必要となります。
2. 登記変更の手続き
不動産を正式に売却するには、名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。これが「相続登記」です。遺産分割協議書や戸籍謄本、固定資産評価証明書などの書類を揃えて法務局に申請します。2024年4月から相続登記は義務化され、期限内の手続きが求められるようになっています。
3. 不動産会社の査定
登記変更が完了したら、次は不動産会社に査定を依頼して売却価格の目安を把握します。複数社に見積もりを依頼して、相場を知ることが大切です。また、複数の不動産会社に査定を依頼することで比較・検討でき、希望に合った会社を選ぶことができます。
4. 不動産会社と契約
査定結果をもとに売却を依頼する不動産会社を決めたら、「媒介契約」を締結します。契約には「専属専任」「専任」「一般」の3種類があり、売主の希望に応じて選択可能です。具体的には販売を急ぐ人は「専属専任」「専任」、じっくり売りたい人は「一般」を選ぶと良いでしょう。この契約をもとに、不動産会社が販売活動を行い、買主を探します。
5. 不動産の引き渡し
買主との売買契約が成立し決済が完了すると、いよいよ不動産の引き渡しです。売主側は必要書類の準備を行い、司法書士立ち会いのもとで所有権移転登記が行われます。これで売却手続きは完了し、売却代金を受け取ることができます。
相続した不動産を売却する際の注意点とは?

相続した不動産を売却する際には、事前に把握しておくべき注意点がいくつかあります。
これらを理解し、適切な対応をとることが大切です。
相続登記の義務化と売却への影響
2024年4月から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました 。相続登記を行わないと、不動産の売却ができないだけでなく、他の相続人が勝手に持ち分を登記して売却するリスクもあります。また、相続人が亡くなるとさらに相続人が増え、売却や管理が困難になる可能性もあります。相続した不動産を売却する際は、まず相続登記を済ませることが大切です。
税制特例の適用期限
相続した不動産を売却する際には、「取得費加算の特例」や「空き家の3,000万円特別控除」などの税制特例を利用できる場合があります。これらの特例には適用期限があるので注意が必要です。例えば、「取得費加算の特例」は相続開始から3年10ヶ月以内(将来的に変更の可能性あり)、「空き家の3,000万円特別控除」は相続開始から3年以内に売却する必要があります。売却手続きには時間がかかるため、早めに行動し、特例の適用期限を逃さないようにしましょう。
遺産分割協議書の記載内容
相続した不動産を代表者の名義で売却し代金を相続人で分配する場合、その旨を遺産分割協議書に明記しておく必要があります。この記載がないと、売却後に代表者が分配した遺産が他の相続人に対する贈与とみなされ、贈与税が発生するおそれがあります。遺産分割協議書を作成する際は、売却の目的や分配方法を明確に記載し、相続人全員の署名と押印を行いましょう。
まとめ
今回は、相続した不動産を売却するタイミングや、税金の種類について解説してきました。
相続した不動産の売却を検討する際には、さまざまな要因を総合的に考慮する必要があります。相続税の納付状況や資金の余裕、不動産の活用予定の有無などが、売却のタイミングを判断する重要なポイントとなります。
売却によって現金化することで、納税資金の確保や維持費の軽減といったメリットが得られる一方で、譲渡所得税や住民税、復興特別所得税などの税負担が発生するデメリットもあります。
また、売却の際には注意すべき点も多岐にわたるため、専門家の助言を得ながら最適な売却時期と方法を検討することが大切です。