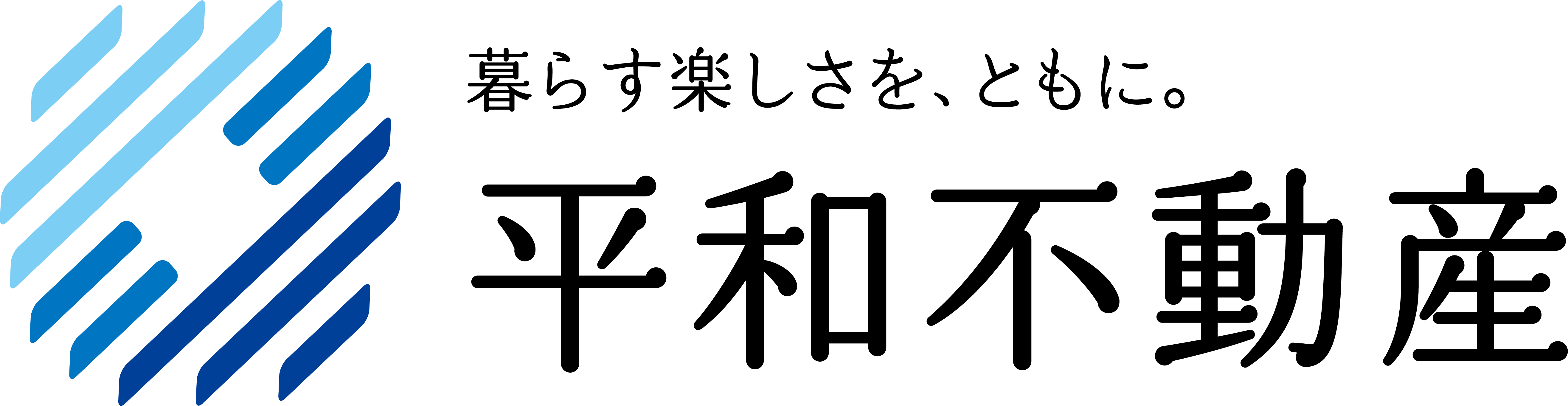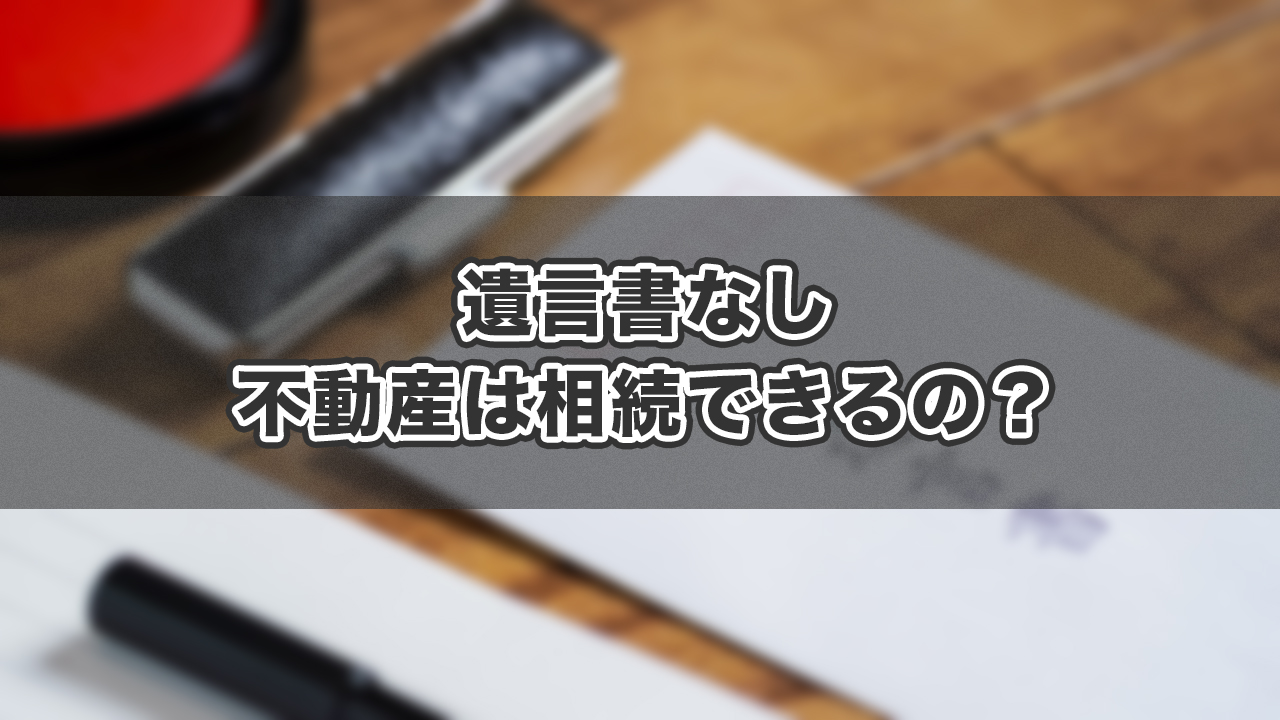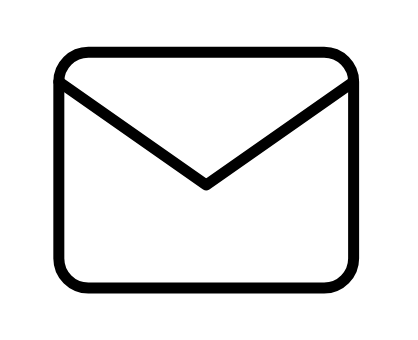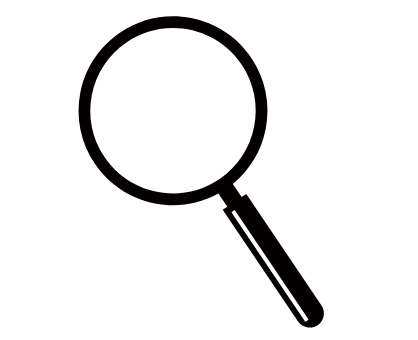「親族が不動産を所有していたけれど、遺言書が残されていなかった…」
そんな状況に直面すると、「この不動産、相続できるのだろうか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
不動産の相続は現金や預金と比べて手続きが複雑になりやすく、遺言書の有無が大きなポイントとなります。では、遺言書がなかった場合、どのように相続手続きが進められるのでしょうか。
この記事では、遺言書が存在しない場合の不動産相続の流れや必要書類、注意点まで詳しく解説します。
遺言書がなくても不動産は相続できる?

結論から言えば、遺言書が存在しなくても不動産を相続することは可能です。ただし、遺言書がない場合は「誰がどの財産を相続するか」について、民法に基づく法定相続人の間で協議する必要があります。
例えば、配偶者や子どもが相続人となり、法定相続分に基づいて財産が分配されます。
ただし不動産は現金のように単純に「分ける」ことができないため、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行い、不動産を誰が取得するか、共有にするか等を決める必要があります。
話し合いがまとまらない場合は、不動産を売却して現金化し分ける「換価分割」や、特定の相続人が取得し代償金を支払う「代償分割」といった方法も検討されます。
さらに、2024年4月からは「相続登記の義務化」が始まり、相続を知った日から3年以内に不動産の名義変更手続きを行わなければ、10万円以下の過料が科される場合があるため注意が必要です。
遺言書がない場合の不動産相続の3つの方法
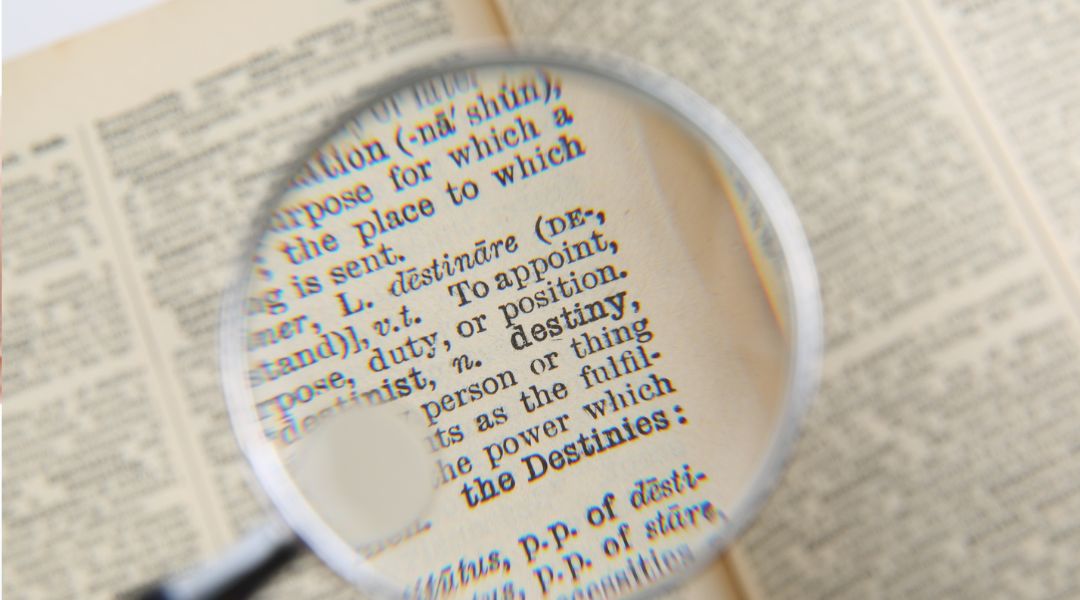
遺言書が存在しない場合、不動産相続は次の3つの方法で進められるのが一般的です。
1. 法定相続分による共有
遺言書がなければ、民法で定められた法定相続分に基づいて財産が分けられます。不動産も例外ではなく、相続人ごとの持分割合に応じて共有する形が一般的です。
例えば、配偶者と子ども1人が相続人であれば、それぞれ1/2ずつの持分となり、不動産の登記名義も共有登記が必要です。
ただし、共有状態のままでは将来的な売却や管理で意見の対立が生じやすく、トラブルの原因になるケースも少なくありません。
2. 相続人全員による遺産分割協議
不動産を誰が取得するか、共有にするか、代償金をどう支払うかといった内容を、相続人全員で話し合って決めるのが遺産分割協議です。
協議がまとまった場合は「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印で押印します。その後、この協議書を基に相続登記(名義変更)を行います。
なお、1人でも協議に同意しなければ無効となるため、必要に応じて専門家(司法書士や弁護士)に相談するのもおすすめです。
3. 家庭裁判所での調停・審判
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てます。調停では中立的な調停委員が仲介し、合意点を探ります。それでも合意できなければ審判へ進み、裁判所が最終的な分割方法を決定します。
この場合、時間や費用がかかるほか、相続人同士の関係が悪化するリスクもあるため、できるだけ協議での解決を目指すのが理想です。
遺言書がない場合の不動産相続に必要な書類

遺言書がない場合、不動産相続を進めるためには以下の書類が必要です。
戸籍謄本一式
被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までのすべての戸籍」を収集します。これには、除籍謄本や改製原戸籍も含まれます。
これにより法定相続人の範囲が確定します。さらに、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となるため、早めの準備が重要です。
遺産分割協議書
相続人全員の合意内容を記載し、全員が実印を押印した協議書です。不動産の相続登記だけでなく、銀行口座・証券口座・自動車の名義変更などにも必要になる場合があります。
相続登記申請書
不動産の名義を変更するために法務局へ提出する書類です。
申請書には被相続人と相続人の情報、登記原因、相続日などを正確に記載する必要があります。また、以下の書類も添付するのが一般的です。
-戸籍謄本(被相続人・相続人)
-遺産分割協議書
-固定資産評価証明書
-相続関係説明図(作成を求められる場合が多い)
まとめ
遺言書がない場合でも不動産の相続は可能ですが、法定相続人による遺産分割協議や、必要に応じて家庭裁判所での調停・審判が必要になります。
また、2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、相続を知った日から3年以内の登記申請が法律で義務づけられています。
トラブルを避け、スムーズに相続手続きを進めるためには、戸籍謄本一式・遺産分割協議書・登記申請書などの必要書類をしっかり揃え、必要に応じて専門家に相談しましょう。