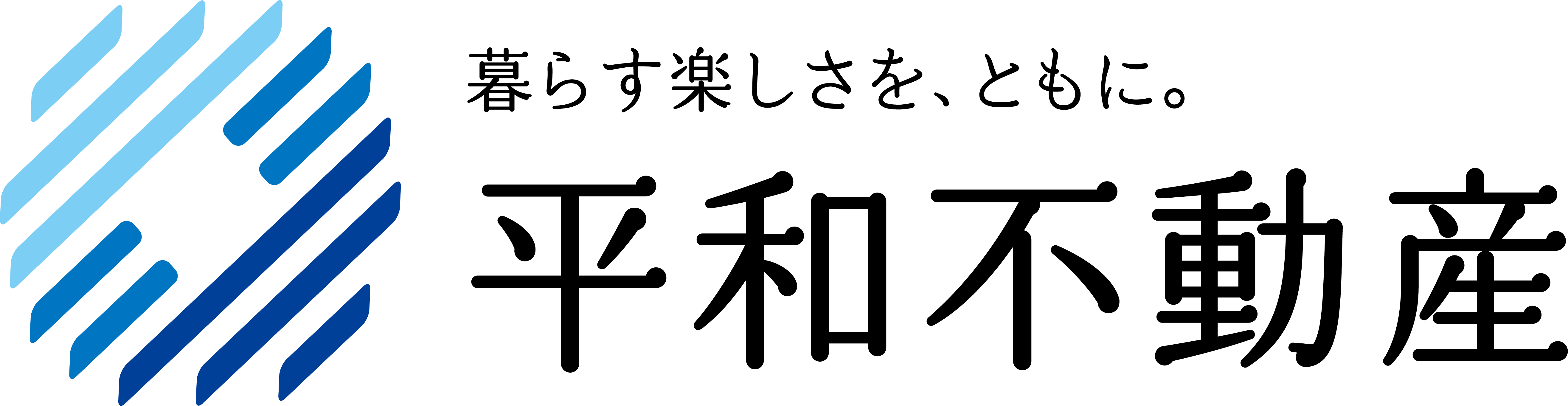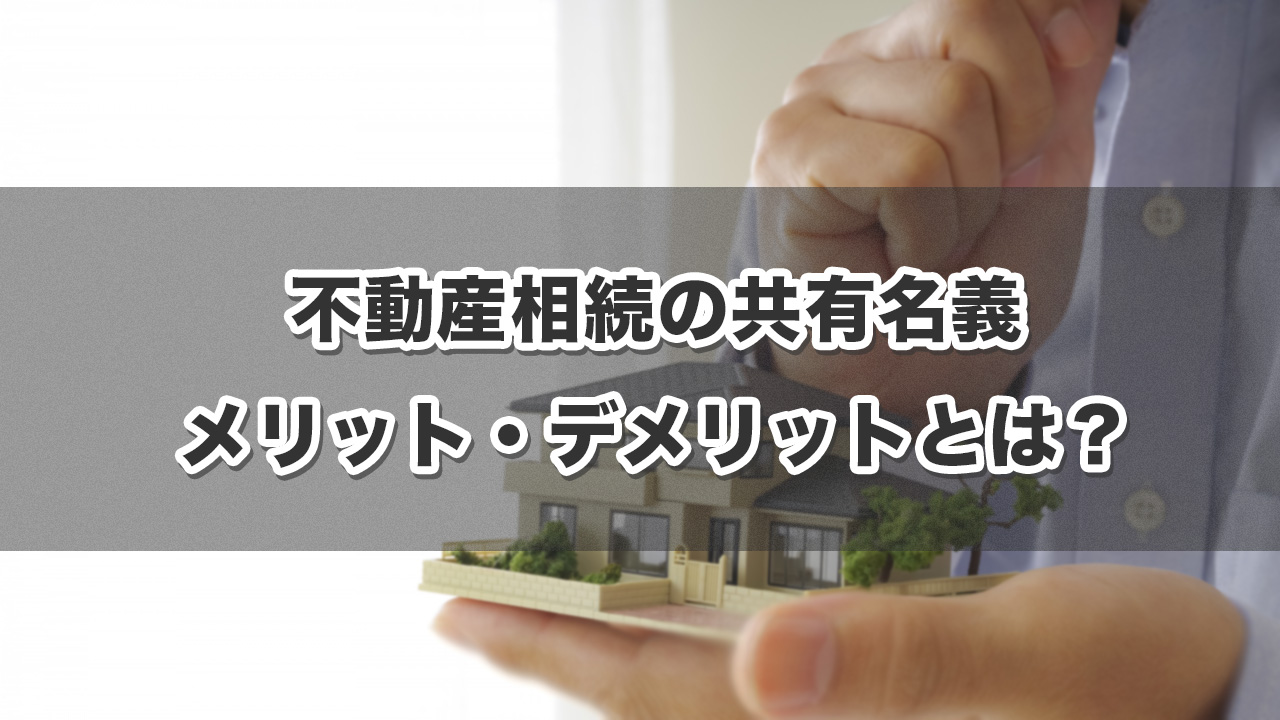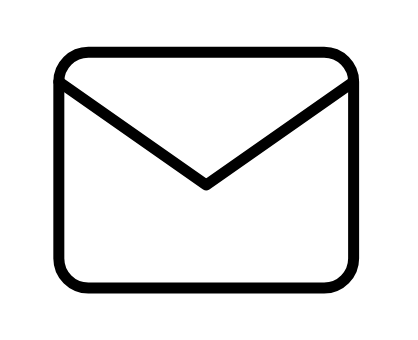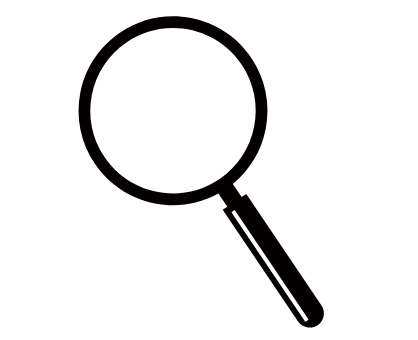不動産を相続するとき、選択肢の一つに「共有名義」があります。
相続人全員が権利を持つ形は一見平等で、分けづらい不動産においては便利な解決策のようにも感じられる一方で、後々の管理や売却の場面で大きな影響を及ぼす可能性があるのです。
果たして、不動産を共有名義にするのは賢い選択なのでしょうか?
この記事では、不動産相続における共有名義のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
不動産相続の共有名義とはどういうもの?

不動産相続における「共有名義」とは、土地や建物などの不動産を複数の相続人が共同で所有する形態を指します。
例えば、配偶者と子供が相続人の場合、相続税法や民法の定める法定相続分(配偶者1/2、子供各1/4など)に従って、不動産を共有するケースが典型的です。共有名義では「持分」と呼ばれる所有割合が定められ、それぞれの相続人がその割合に応じた権利を持つことになります。
共有名義の特徴の一つに「遺産分割協議を早く終わらせられる」という点があります。相続人全員の同意が得られにくい場合でも、法定相続分に基づいて共有登記が済ませられ、相続登記の義務にも柔軟に対応できます。一方で、将来的に思わぬ負担やトラブルが生じる可能性もあります。代表的な例として、売却や賃貸など不動産を処分・活用する際に、共有者全員の同意が必要になり、一人でも反対すれば進められない点が大きな障害になります。
このように共有名義とは、分割できない財産の権利を複数人で持つことで公平性は保たれるものの、誰がどの部分を管理・利用できるのかが曖昧になりやすいため、所有範囲を巡って争いが起こりやすい仕組みでもあるのです。
共有名義人の片方が死亡した場合、相続はどうなる?

不動産は単独で名義を持つだけでなく、複数人で共有している「共有名義」の場合もあります。登記事項証明書を確認すると、権利部(甲区)の「所有権に関する事項」に「共有者」や「持分」が記載されており、単独名義への変更登記がされていなければ、その物件は共有状態にあると判断できます。
この共有者の片方が亡くなった場合、持分が自動的に残された共有者に移ることはありません。亡くなった方の持分は遺産の一部となり、通常の相続財産と同様に相続手続きを経て相続されることになります。この際に相続人となるのは、他の財産と同じく亡くなった所有者の法定相続人です。したがって、共有名義の不動産においても、持分を有していた方の相続人がその権利を受け継ぐ仕組みとなっています。
なお、相続順位には決まりがあり、配偶者は常に相続人となります。そのうえで、子供が第1順位、両親などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位と定められています。
不動産相続の共有名義のメリット
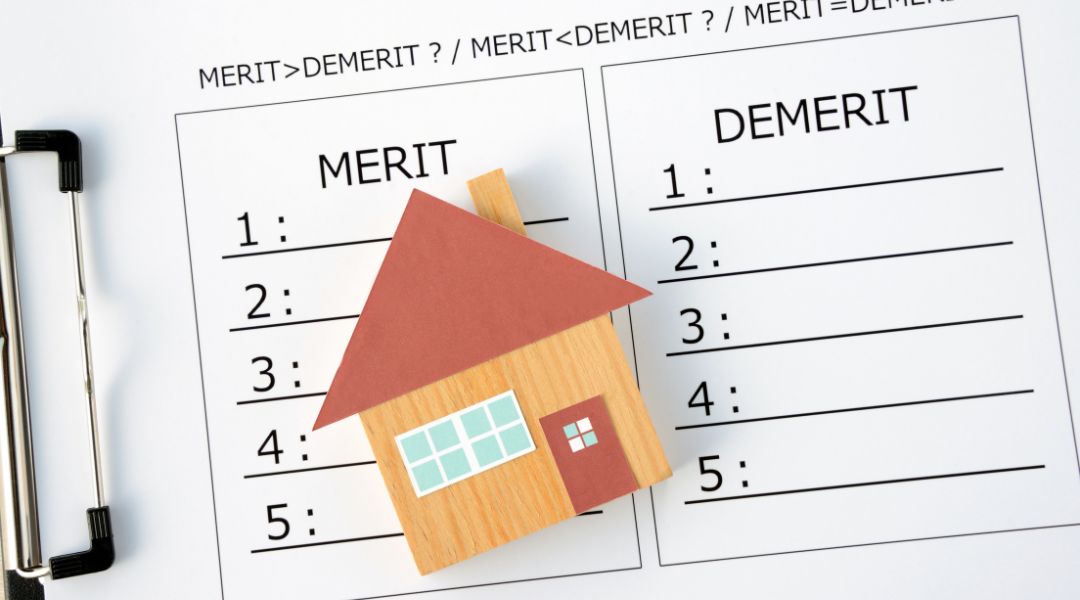
不動産を相続する際に共有名義を選ぶことには、相続人全員が納得しやすく、維持や管理の負担が公平に分けられ、売却時には控除特典による税負担軽減が得られるなど、複数のメリットがあります。
相続人同士が納得して遺産分割協議を行える
不動産を共有名義にすることで、分割しづらい資産を「持分」という形で相続人全員が権利を持つ形になります。これにより、誰かが単独で取得するよりも公平感が生まれやすくなり、円滑な遺産分割協議がしやすくなります。特に、不動産以外の資産が少ない、もしくは不動産一つしかないようなケースでは、代償金の調整などによる争いを回避できるというメリットがあります。また、共有名義にすることで相続人全員が平等に財産を承継できるという意識が働き、心理的な納得感を得やすい点も大きなメリットです。
将来的に不動産を売却する場合にも、持分に応じて利益や費用を分配できるため、分け方が明確で分かりやすいというメリットもあるでしょう。
不動産の維持管理費用や諸経費を分担できる
不動産を共有名義にしておくと、固定資産税・修繕費・火災保険料・都市計画税などの維持管理に必要な費用を持分割合に応じて分担できます。これは民法上の原則であり、各共有者が公平に負担する仕組みで、過度な出費を特定の相続人に集中するリスクを下げられます。さらに、代表者が立て替えて支払い、他の共有者に求償することも可能で、手続き上も業務的に分担が進めやすくなります。
共有名義にすることで、不動産を保有しているという責任感を相続人同士で共有でき、結果的に維持管理に対する協力意識が高まることも期待できます。
長期的に見れば一人で全てを背負うよりも、経済的にも精神的にも負担を減らせるでしょう。
売却時に税金の控除額が増加する
共有名義の不動産を売却する際、居住用財産であれば「3,000万円特別控除」が名義人それぞれに適用されるため、控除額が名義人の人数分まで増える可能性があります。例えば、共有名義が2人であれば最大6,000万円の控除枠が生まれ、税負担を大幅に軽減することが可能です。
共有名義にしておくことで、売却後の利益分配も持分に応じて公平に行えるため、金銭トラブルの防止にも繋がります。
相続後すぐに売却を検討する場合だけでなく、将来的に手放す際の選択肢としても、節税効果を得ながらスムーズな資産処分が可能となる点は大きなメリットと言えるでしょう。
不動産相続の共有名義のデメリット
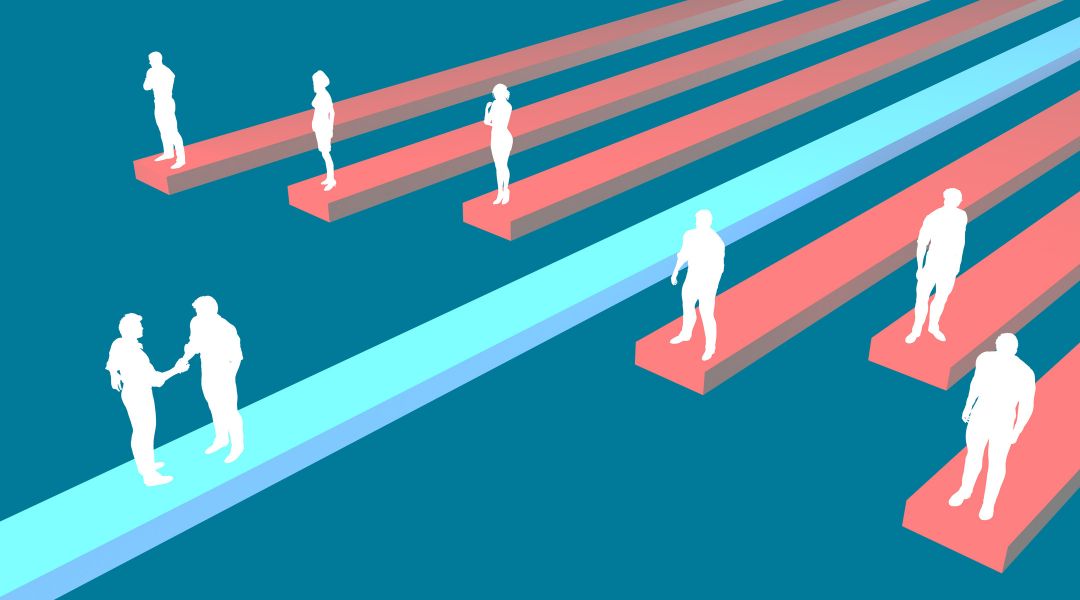
相続した不動産を共有名義にすると、管理や処分の自由度が低下し、税や維持費の負担調整に課題が生じることがあります。また、将来的に共有者が増え続けることで、共有者を見つけることすら困難になります。共有名義を選ぶ場合は、これらのリスクがあることを事前に把握しておくことが大切です。
不動産の活用や処分には全員の同意が必要
共有名義にした不動産は、売却・取り壊し・リフォームなどの大きな変更を行う際には、共有者全員の合意が求められます。仮に持分が90%の共有者が提案したとしても、10%の持分を持つ共有者が反対すればこれらの行為は一切行えず、不動産が事実上 “塩漬け” になることでしょう。さらに、売買契約や登記手続きでも共有者全員による署名・印鑑証明・本人確認が必要なため、遠方に住む共有者がいると手続きに手間と時間がかかります。
不動産を賃貸として活用する場合などの「管理行為」における意思決定においても、過半数の合意が必要とされるため、共有者の数が多かったり意見が対立している場合には、そもそも意思統一が困難になる点が大きな弱点です。
固定資産税を分割して負担するのが難しい
共有名義の不動産は、固定資産税や都市計画税などの納付義務を共有者全員が連帯で負いますが、税金の納付通知は代表者一名に送られます。そのため、代表者が全額納めた後、持分に応じて他の共有者から徴収する仕組みが一般的ですが、他の共有者が応じない場合、代表者が実質的にその分を負担せざるを得なくなるのです。
代表者が支払わなかった場合には、他の共有者に市町村から督促が届くなど、共有者間の関係が緊張する要因にもなります。こうした状況は、財務的な負担だけでなく、心理的なストレスや親族間の不信感にも繋がるでしょう。
共有名義にする場合は税負担の分担ルールや事前の合意を明確にしておくことが欠かせません。
ねずみ算式に共有者が増加してしまう
不動産相続を共有名義にすると、相続が重なるたび「ねずみ算式」に共有者が増えるリスクがあります。ある共有者が亡くなり、その持分を配偶者や子が相続することで、当初の共有者が見ず知らずの親戚や遠縁の者にまで広がる可能性があります。こうした状況に陥ると、誰が共有者か把握できなくなり、連絡や意思統一が極めて難しくなります。
疎遠な親族が加わることで、不動産の売却や管理の意思決定に混乱が生じ、対応が遅れてトラブルや資産の停滞を招くことがあるでしょう。また、共有者が増えるほど各自の持分が小さくなり、売却や意思決定の効率がさらに下がるため、管理や売却の手続きを行う際に大きな負担となってしまいます。
共有名義による不動産でよくあるトラブル事例とは

共有名義による不動産は、相続や共同所有の形態として一般的ですが、その運用にはさまざまなトラブルが発生する可能性があります。
以下では、共有名義の不動産でよく見られるトラブル事例を3つご紹介します。
1. 不動産の活用・売却で共有者間で意見対立が起こる
共有名義の不動産では、売却や賃貸としての活用、リフォームなどの意思決定には、共有者全員の同意が必要となります。しかし、共有者の意向が一致しない場合は意思決定が滞り、不動産が長期間活用できなくなるのです。
例えば、一部の共有者は売却して現金化したいと考えても、他の共有者が思い出のある建物を残したい場合、話がまとまらず計画が頓挫してしまいます。意見が対立することで共有者間の関係が悪化し、心理的負担が増すケースも少なくありません。
こうした状況を避けるには、定期的な話し合いや、活用方針を事前に文書で取り決めておくことが有効です。
2. 共有持分を無断で売却される
共有者の一人が自分の持分を無断で第三者に売却するケースもあります。このような場合、他の共有者の同意を得ていない売却は原則無効となりますが、トラブルに発展する可能性は高いです。無断での売却が行われると、第三者が新たな共有者として加わり、意思決定や活用がさらに困難になります。また、共有者間での信頼関係も損なわれ、場合によっては法的手続きで解決を図る必要が生じることもあるのです。
共有持分の売却については事前に共有者全員の合意を文書化し、公正証書や登記などの法的手続きを適切に行う必要があります。
3. 共有者が認知症になり、不動産を活用・売却できなくなった
共有者の一人が認知症などで判断能力を喪失した場合、その持分に関する意思決定ができなくなり、不動産の活用や売却が滞ってしまいます。結果として、資産の有効利用ができず、共有者全体に不利益が生じる場合があるのです。また、判断能力を喪失した共有者の代理人との交渉や法的手続きが必要となるため、時間や費用がかかることも少なくありません。
このリスクを回避するためには、共有名義にする前に判断能力の確認や、成年後見制度の活用、事前委任状の作成など、万が一に備えた準備を行っておくことが大切です。
まとめ
今回は、不動産相続における共有名義のメリット・デメリットについて解説しました。
不動産相続における共有名義とは、複数の相続人が持分を分けて所有する形であり、公平性を保ちながら遺産分割を円滑に進められるメリットがあります。また、維持管理費や固定資産税を持分に応じて分担でき、売却時には控除額の増加による節税効果も期待できます。
一方で、共有者全員の同意がなければ活用や売却ができず、意思決定が滞るリスクがあります。また、共有者の一部が無断で持分を売却したり、認知症などで判断能力を失った場合には、不動産の管理や処分が困難になり、トラブルや手続きの複雑化を招くことも少なくありません。
このため、共有名義にする際はメリットとデメリットを十分理解し、共有者同士で事前に話し合いを進めておくことが大切です。