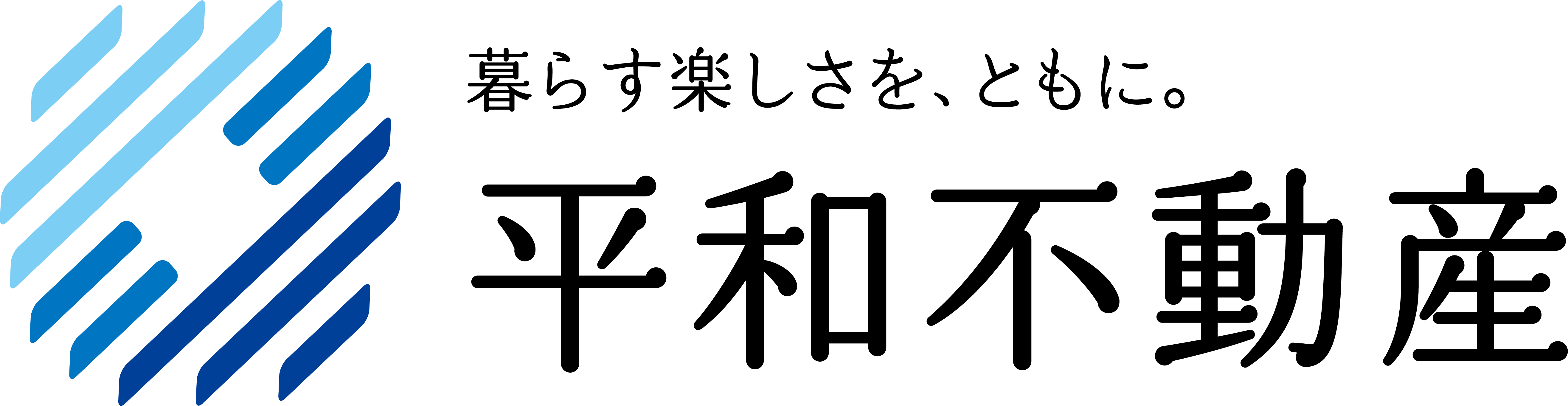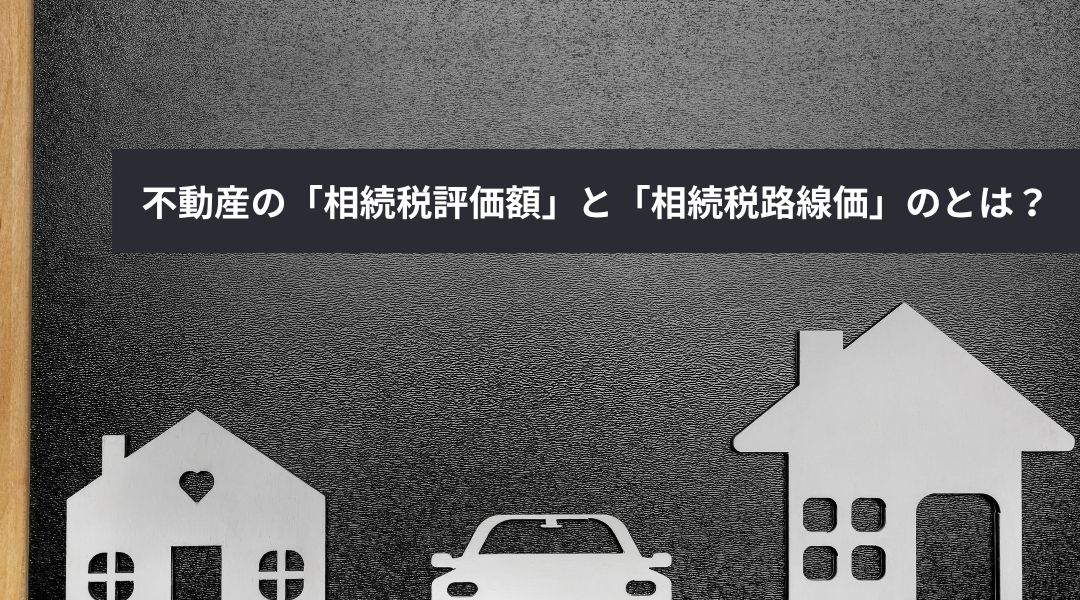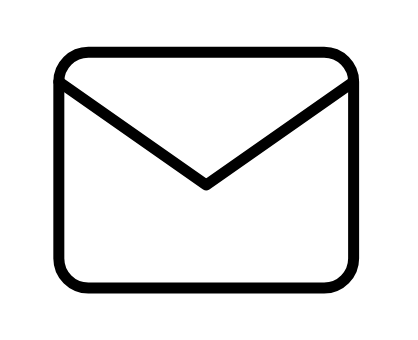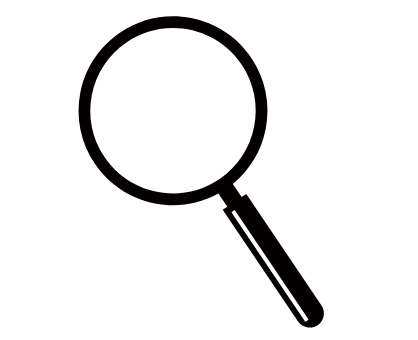親族から不動産を相続することになったとき、税理士や不動産会社から「相続税評価額」や「相続税路線価」という専門用語を耳にすることがあるでしょう。一見すると同じような意味合いに感じますが、実はこれらには異なる役割と意味があるのです。
これらは、相続税の計算や土地の評価額に直結する重要な指標であるため、これらを理解することはとても大切です。
この記事では、相続税評価額や相続税路線価について詳しく解説していきます。
「相続税評価額」や「相続税路線価」について

不動産の相続税の計算では、「相続税評価額」やその算出の際に「相続税路線価」を用います。
どちらも相続税の計算に欠かせない要素であるため、正しく理解しておきましょう。
「相続税評価額」とは?
相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算する際に使われる不動産の評価額であり、国が定める評価方法に基づいて算出されます。
土地の評価には「路線価方式」または「倍率方式」があり、建物は原則として固定資産税評価額を用います。路線価方式は、土地が面する道路に設定された1㎡あたりの相続税路線価に土地の面積や形状補正などを加味して求める方法です。一方の倍率方式は、固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率をかけて算出されます。
相続税評価額は実際の売買価格(時価)よりも低く設定されるのが一般的で、時価の約80%程度とされています。評価方法により結果が異なるため、立地や土地の条件によって適用される評価方式も変わってきます。なお、評価額は申告時の基準日(原則1月1日)に基づき計算され、毎年見直される点も注意すべきポイントです。
「相続税路線価」とは?
相続税路線価とは、市街地の道路に面する土地1㎡あたりの評価額として、国税庁が毎年公表している指標です。この路線価は、その道路に接する土地の相続税評価額を算出するための基礎データであり、「路線価方式」において最も重要な役割を担っています。
相続税路線価は、公示地価(一般の市場価格に近い価格)の約80%を目安に設定されており、これにより実勢価格と税額のバランスが保たれています。固定資産税で用いられる路線価(基準地価の約70%)や実際の売買価格とは異なるため、土地の評価額には複数の「ものさし」があることを理解しておく必要があります。
また、相続税路線価は道路単位で行われているため、同じ町内でも道路によって土地の評価額が変わることがあります。不整形地や間口の狭い土地などは補正率が適用されることで、より実態に即した評価が行われます。
このように、相続税路線価は相続税、贈与税を計算する際に使われる数値であり、他の要素と組み合わせて用いられるのが特徴です。
相続税路線価の調べ方について

相続税路線価を調べる方法はいくつかあります。国税庁の公式サイト、地図ベースの民間サービス、さらには図書館の資料まで。正確な相続税評価を把握するために、用途や目的に応じた方法を選びましょう。
国税庁ホームページ「路線価図・評価倍率表」から検索
相続税路線価を正確に知るためには、国税庁の「路線価図・評価倍率表」を活用するのが最も基本かつ信頼性の高い方法です。都道府県から市区町村、町丁目を選択すると、その地域の路線価図が閲覧できます。路線ごとに1㎡あたりの価格が表示され、補正率の記載もあるため、実際の評価額計算にも役立つでしょう。倍率地域に該当する土地は、固定資産税評価額に「倍率表」の数値を掛けて算出します。
誰でも無料で利用でき、税理士だけでなく一般の方の調査にも広く活用されています。
全国地価マップを活用する
全国地価マップは、公益法人が提供する地図ベースの不動産評価支援ツールです。
住所や地番で簡単に検索でき、地図上に相続税路線価・固定資産税路線価・地価公示価格などが視覚的に表示されます。初心者でも直感的に使える点が好評で、周辺エリアとの価格比較も一目で確認可能です。また、複数年分の路線価データを切り替えて表示できるため、地価の推移を把握したい人にも便利です。スマホでも快適に閲覧できるので、現地での確認にも活用できます。
図書館で過去の路線価図を確認する
ネット上で公開されていない古い相続税路線価を調べたい場合には、国立国会図書館や都道府県立図書館を利用するのがおすすめです。これらの施設には過去の「財産評価基準書」や「路線価図・評価倍率表」が保管されており、相続税に関する歴史的資料を調べる際にも活用できます。
一部の古い路線価図は国立国会図書館の「WARP(インターネット資料収集保存事業)」でも電子化されており、PCからの閲覧が可能です。地方自治体の図書館でも閲覧できることがあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
相続税路線価をもとに税計算する際の注意点とは

相続税路線価を使った不動産評価では、年度や土地条件によって結果が大きく変わります。
税計算をする際は正確な評価が求められるため、特に以下の3点に注意が必要です。
相続開始年の路線価を使用する
相続税路線価は毎年7月に前年度1月1日時点の時価で発表されますが、税計算で使用すべきなのは被相続人の死亡年の「その年の」路線価だけです。例えば、1~6月に相続が発生すると、路線価が公表される7月まで正式な相続税評価額を算出できません。
誤って別年度のデータを用いると、税額や控除額にずれが生じ、税務署から指摘や修正申告を求められる可能性があるため、必ず該当年の路線価を確認してください。
土地の形状や接道条件に応じた補正が必須
路線価×面積の計算では実際の価値を正確に反映できません。不整形地・奥行長大・間口狭小・がけ地・角地などは、「奥行価格補正率」「不整形地補正率」「側方路線影響加算率」などを適用した調整が必要になります。
これらの補正を怠ると評価額が過大または過小となり、税負担が不適切に重くなったり、税務調査で差額の追徴やペナルティを課せられるリスクがあります。土地の形状・接道内容に応じた補正を正しく適用することが大切です。
路線価がない地域では倍率方式で評価する
市街地以外の地域では相続税路線価が設定されておらず、固定資産税評価額に国税庁の「評価倍率」をかける「倍率方式」を用います。この倍率は地域・地目ごとに異なります。さらに、倍率地域でも周辺宅地価格と比較する「比準方式」が必要になる場合があり、形状補正が必要なケースもあります。また、同じ土地で路線価地域から倍率地域に変更される場合もあるため、その年の該当方式を確認し、誤用しないよう注意が必要です。
まとめ
今回は、不動産の「相続税評価額」と「相続税路線価」について解説してきました。
相続税評価額は、実際に相続税を算出するための基準となる金額で、土地や建物に対して国が定めた評価方法に基づいて決定されます。一方の相続税路線価は、その評価額を求めるために使われる基礎的な指標であり、特に市街地における土地評価では路線価方式として活用されます。
つまり、相続税路線価は評価額を算出するための「材料」、相続税評価額はその結果として得られる「完成品」と言えるでしょう。
評価額の算出には、国税庁の公式ホームページや全国地価マップ、図書館の資料などを活用することで求めることが可能です。